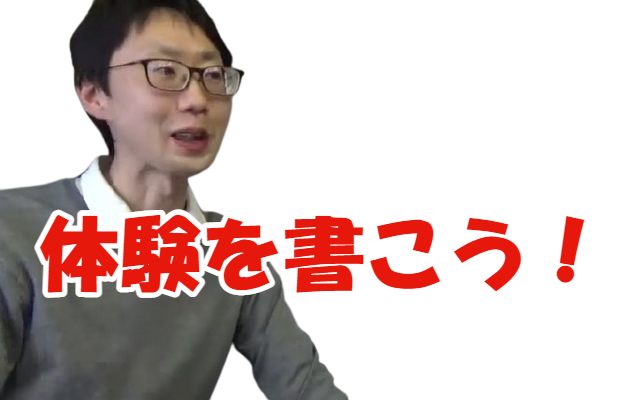つくづく、言葉というのは面白いな、と思う。
言葉がなくては、思考ができぬ。けれども、言葉が思考を制限する。
言葉がなくては、意思の疎通ができぬ。けれども、言葉があるから、誤解が生まれる。
昔は、本が大好きだった。というより、文章が好きだった。理由はない。というよりは、思い出せないのだ。知らないことを知ることが出来るだとか、空想の世界に行けるだとか、新しい言葉を覚えるのが楽しいだとか。いくらでもこじつけることはできるけれど、どれも違う。気づいた時には好きだった。まるで、どこかのありふれた恋愛ソングみたいに。さながら、当時の私は文章に、文字に、恋をしていたのかもしれない。
今思えば、両親の影響のようにも思う。記憶にはないが、幼い頃は母がよく絵本を読み聞かせしてくれていたようだし、両親共にそこそこ本を読む人だ、多分。実家には今でも世界文学全集・日本文学全集がある。そうは言っても、妹は私のような「本の虫」タイプではなかったから、私自身にも何かしら本好きになる素養があったのかもしれない。
小学校の頃は、私が行きたがるからか、自分が行きたいからか、よく地元の図書館に連れて行ってくれた。貸出期限が3週間なので、3週間に一度のペース。毎回読み切れないほど大量の本を借りて、読み切れなかった分はまた次の3週間で借りて。学校の教室の本もあったし、図書室の本もあった。私の周りは、読みたい本であふれていた。
多かったのはファンタジーやSF。有名どころだとハリー・ポッターやナルニア国物語、星新一。図書館だから最新の本はあまりなかったけれど、それでも十分だった。高学年になるにつれ実用書の類も借りるようにはなったけれど、結局あまり読まないままに返すことが多かった。
それから、本に限らず広告やレストランのメニュー表、街の案内表示なんかも片っ端から読むのが癖だった。トイレの便座に座れば、必ずウォシュレットだの禁煙だのの表示を読んだ。どこにいってもほとんど定型文なのだけれど、それでも毎度、目で追った。小学校と家だけの狭い狭い世界の中で、文字を追うことが、私のほぼ唯一の娯楽だったのだ。特段厳しい家だったわけではない。ゲームやおもちゃも買ってもらったし、テレビを禁止されていたということもない。人並みに遊んでいたとは思う。けれども今振り返ってみると、どこかぬぐえない義務感のようなものがあった気がする。当時は自分で気が付いていないから、おもちゃを買ってもらったら喜んだし、友達ともそれなりに楽しく遊んでいたはずなのだが、小学校時代のそれらの思い出は私の中にほとんど残っていない。思い出すのは読書中に友達に外へ連れ出されようとしている光景と、帰りの準備の時に流されていた流行りのJ-pop、当時習っていたピアノのメロディ。そしてその時々に現実から離れてはぼんやりと頭に思い描いていた、読みかけの小説のストーリー。
それから、音読の宿題も1年から6年まで欠かさずやった。いや、欠かさずということはないが、やらなかった日の分は後日まとめてやっていた。これに関してはしぶしぶだったし、毎度母に叱られながらではあったが、読み始めるとそこまで苦痛なわけでもなかったし、物語の時は存外楽しく読んでいた。今でも時々、気分転換に朗読をするくらいには、これも馴染みの習慣だ。周りを見ていると、6年まで律儀に親の前で音読をしている、というケースは少数のようだった。
中学にあがり、毎日部活や宿題に追われるようになると、本を読む機会は一気に少なくなった。それでも国語の授業は好きだったし、授業中はよく本を読んだり、国語の便覧を眺めたりしていた。家では、食事中に本を読んでいては怒られるので、広告や新聞を目に届くところに置いて横目でこっそり読んだ。それでも、大概はバレて怒られるのが常だったけれど。
高校にあがると、部活に入らなかったので随分と時間の余裕ができた。それでも、一度手放した読書習慣というものは戻らなかった。スマホを手にしたり、行動範囲がぐっと広がったりしたことも大きかったのかもしれない。小学生の頃と違って、私の周りにはありとあらゆる娯楽が溢れていた。ただ、そんな娯楽たちに負けないくらいに、高校の現代文は面白かった。高校の先生というのは、たいてい自分の担当科目が好きなものだ。私立の学校となると、輪をかけて個性的な人が多い。その先生も例に漏れずザ・国語オタクの風変りな人で生徒からの評価は大きく分かれていたが、私は大好きだった。とはいえ、授業の内容をきちんと覚えているわけではないのだけれど。
思い出せるのは、RADWIMPS「天体観測」の歌詞の読み解きをしたこと。「君」が誰なのか、僕との関係性は。そんなことを順に読み解いていく。けれど、これには答えがない。学校の授業ではたいてい正解がある。とはいえさすがに高校ともなれば、自分の意見を書きなさい、という場面もないではないが、読み解きの時点で正解がないケースは珍しくて新鮮だったことを覚えている。
センター試験の現代文は、ほとんど勉強した記憶がない。いや、していないわけではないが、間違えることの方が少なかったし、何より自分では選んでこない文章をたくさん読める機会だったので、あまり勉強という感じはしなかった。先生は、一応は解き方のコツなんかを教えながらも「僕はなんで分からないのかが分からないんですけどね。」なんて言って、一部の人からは反感を買っていた。私はけれど、それに心底同意していた。時間内に解けないというだけならまだしも、時間をかけても間違うだなんて。一体何が分からないのかが、さっぱり分からない。読めば答えが書いてあるじゃないか。解き方を覚えて使いこなすよりも読んだ方が圧倒的に早い。
この時に、私は初めて、読んでも「分からない」人がいることを目の当たりにした。断っておくが、私は決して賢いわけでも地頭がいいわけでもない。謙遜でもなんでもなく、事実そうなのだ。人より話が理解できていないことも多々あるし、理数も英語もからっきし。同じ日本語でも、単語に馴染みがないからか法文の類はさっぱり頭に入らない。それでも、昔から文章に親しみすぎるくらい親しんできたおかげで、平均以上には読解力を身に着けていたらしい。この時ほど親に感謝したことはない。幼少期の読書&音読習慣は、私にとっては様々な意味で財産となっている。
現代文の他にも、私が通っていた高校には個性的な先生が多かった。どの授業だったかどの先生だったか、語り口調も文脈もさっぱり忘れてしまったのだが、とにかく高校の授業の中でとても印象的だったことがもう一つある。(国語か、英語か、倫理か宗教か。とにかくそのあたりだ。)端的に言えば「言葉が物事に輪郭を与えるのだ」という話。虹は日本では7色だけれど、どこかの国では10色で、どこかの国では6色で、またどこかの国では2色だそうだ。区切って、名前を付けて初めて、そこに姿を現すのだ、ということだった。確かに虹はグラデーションになっているし、どこで色の切れ目があるのか曖昧だ。だから10色にも6色にも見えなくはないが……2色!?衝撃だった。あのカラフルな色を2つにしか捉えられないのは、なんというか……もったいない。直感的に、そう思ったのだ。だからたくさんの言葉を知って、できるだけ世界を鮮やかに認知できるように、そして表現できるようになりたいと、当時の私は思ったのだ。
この出来事が強く印象に残ったせいか、これ以降私は、こういった類の話に非常によく食いつくようになった。覚えているだけでもいくつかある。
日本で髭は「髭」という一つの単語に部位(口とか顎とか)をつけて表現するけれど、英語では髭の部位によってそれぞれ別の単語があるらしい。そうやって単語がたくさんある事柄は、その国で重要視されているから単語が増えてその周辺事象の言語が発達していくのだ。だから外国語を学ぶ時に、日本の単語と外国の単語が1対1対応になることはあり得ないのだ、とか。
「発達障害」や「引きこもり」「不登校」なんかは、今でいうとその言葉で示されるであろう人たちは昔から存在していたが、そういう言葉で表現されるようになって初めて社会問題化し、表に出てきた。だからその言葉が一般化していくと同時に当事者が増えていくのは、ごく当たり前のことで、実際に「それに該当する人」の数が純粋に増えているかどうかとは別問題なのだ、とか。
言語化することは、果たして良いことばかりなのだろうか。そんな疑問が、徐々に湧き上がってくる。
知れば知るほど、深みにはまっていく。
例えば、言語化することで「マイノリティ」としてくっきりと浮かび上がってしまうことがある。それは特別な配慮をしてもらえる可能性と同時に、これまで「普通」だった人が、そこから切り離されてしまう可能性も持っている。良くも悪くも。
例えば、言語化することでグラデーションがグラデーションでなくなってしまうことがある。虹を7色に分割したとしても、その間の色はなくならない。虹は目に見えるからまだ良いが、目に見えないものを分割してしまったら「その間」はどうなってしまうのだろう。
自分の体感として、一番疑問に思ったのは感情面だった。人に伝える時には、もちろん言語化しなくては伝わらない。けれど同時に、誰に伝える必要もない自分の感情に、無理やり名前をつける必要はあるのだろうか、と。少なくとも私は「虹」の一件以降、随分と感情豊かになった。それまでの私は「嬉しい」とか「悲しい」とか、自分の言葉で説明できる範囲の感情しか持ち合わせていなかった。まさに「言葉で切り取れるものしか認識できない」というそれが、事実であることを示すように。文学的表現のストックもないではなかったが、誰かに伝える予定もないそれを、いちいち頭で意識的に表現し直すような丁寧さはあいにく持ち合わせていない。ではなぜ感情が豊かになったのかと言うと「言葉で表すことのできない感情が存在して良いのだ」ということを学んだからである。色んな思いがないまぜになった「それ」を、「色んな思いがないまぜになった」それではなく、それをそれそのものとして自分の中で大切にできるようになった。誰に説明するわけでもないから、共通理解できるような言葉はない。けれど、自分の中で感情A、感情B、というように、既存の言葉で説明せずともそのままの状態でフォルダに入れて、保存ができるようになった。人に表現する必要がないからこそ、既存の感情を表す言葉に惑わされず、そこに居座る感情そのものを認識するようになった。この変化を私は感情豊かになった、と表現したが、それは決して感情を外に出すようになった、というような表に現れる変化ではなかった。けれども確実に、私が持つ情緒に大きな変化をもたらしたのだ。
今書きながら、気がついたことがある。
それをそれとして認識するという行為は、新しい言葉を与える行為に非常に似通っている。さっき挙げた「髭」の話と同じである。既存の言葉では足りない、表現しきれない。だから新しい切り取り方をすることで、新しい言葉が生まれる。私にはみんなで共有できる新しい言葉を生み出すような芸当は到底できないが、やっていることはきっと同じ。ある物事を、既存の言葉・枠組みに当てはめずに、それに新しい言葉・枠組みを与える。
これは、言葉が事実・事象と1対1対応の=で結ばれているわけではない、という前提があって初めて成り立つことだ。けれど既存の言葉で表現するにしても新しく切り取り直すにしても、他人に伝わらなければ共有は不可能。
言葉を持たない小さな子は、自分の不快をうまく表現できずに癇癪を起こす。そこから学習の不足や、言葉で自身を表現する習慣の不足があると、成長しても変わらず自分の望みや感情、意思を表現できないまま、キレやすかったり物に当たったりする大人になる可能性が高まる。らしい。
やっぱり言葉は大切だな、と思う。人に共有する必要がなければ別にそのままでも良いのだけれど、私の持つ「感情A」は、人に共有することができないまま未だ私の中に燻っている。人より語彙が少ないわけではないから、癇癪を起こすことはないのだが。
最近「裏の意味」を読み取れない人が増えているらしい。
それは一般的に「言語能力の衰えだ」と言われるが、見ようによっては裏表のない率直なコミュニケーションができるようになった、とも言えるかも知れない。自分に裏も何もないから、相手にも裏がないと考える。言葉をそのままその通りに受け取る。
それ自体が良いとか悪いとか、私には言えない。けれど「言葉通り」に受け取って良いのか、それが真実なのか、一度問うてみた方が良いとは思う。仮に「言葉にしたことが本人の伝えたいことなのだから裏は詮索する必要がない」のだとしても、そもそも持っている語彙が人によって全然違うのだ。知らなければ表現できないし、知っていても使いこなせているかどうかは自分にも他人にも分からない。相手が伝えたいことを、相手はきちんと言語化できているのか。自分が伝えたいことは過不足なく相手に伝わっているのか、むしろ自分より相手の方が自分が伝えたいことを理解している可能性もある。
言葉はあくまで、道具なのだ。
使いこなせなければ意味がないし、表面に出てきた言葉に振り回されているようでは「道具に使われている」ことに他ならない。
かくいう私も道具を遊びのために使ってしまい、肝心の目的を見失ってしまう節が多々ある。まあこのブログに限って言えば、目的が遊びなので、一応目的を達成しているとも言えるが。
山もオチもない上、目的も意図もないのだけれど、書きたいだけ書いたのでここらで終わり。気が向いたらきちんとした記事に書き直そうと思う。
本当につくづく、言葉というものは面白い。
↓こちら、クリックして応援いただけると嬉しいです‼